トレンドトピック
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
メンガー 7 弾
カール・メンガーの『経済学原理』(1871年)は、オーストリア学派の創設書です。
原則は、労働コストの価値理論を主観的な限界効用に基づく理論に置き換え、商品は個人の欲求と希少性から価値を引き出し、価値は消費から生産に逆流し、すべての経済現象は個人の選択に根ざしていることを示しました。
1. 主観的価値論
価値は(労働価値理論のように)対象に固有のものではなく、個人が自分のニーズを満たすために商品に割り当てる重要性から生じます。
商品が価値があるのは、商品を生産するのに費やされた労働力やコストのためではなく、欲求を満たすからです。
2. 限界効用
メンガーは、財の価値は、財の全体的な有用性ではなく、最後に消費された単位の限界効用に依存するという原則を導入しました。
例:水は必須ですが、水が豊富であるため、希少なダイヤモンドに比べて限界効用(および市場価格)が低くなります。
3. 商品と注文の理論
彼は商品の階層を開発しました:一次商品:人間の欲求(パン、衣服)を直接満たします。高次商品:一次商品(小麦粉、オーブン、小麦)の製造に使用されます。
高次商品の価値は、実際のニーズを満たす低次商品の生産に貢献する能力に由来します。
4. 因果関係と帰属
価値は消費から生産に逆流します。投入物(労働力、原材料、工具)の価値は、それらが生産に役立つ最終財の価値から生まれるものであり、その逆ではありません。
これは、古典的な生産コスト理論の逆転でした。
5. 価値にとって不可欠な希少性
商品は、需要に比べて希少な場合にのみ「経済財」(つまり、評価と交換の対象となる)になります。
何かが豊富で、努力しなくても利用できる場合(空気など)、それは有用であるにもかかわらず、経済的価値がありません。
6. 価格理論の基礎
メンガー氏は、価格は客観的な「コスト」や労働時間からではなく、交換となる個人の主観的な評価から生じると説明した。
この主観的な基盤は後にオーストリアの価格理論の中心となり、マルクスやリカルドとははっきりと区別されました。
7. 方法論的個人主義
経済法則は、「階級」や「社会」などの集合体からではなく、個々の主体の選択と好みから導き出されなければなりません。
この方法論的出発点は、オーストリア経済学をマルクス主義やその後の数理経済学と区別しました。
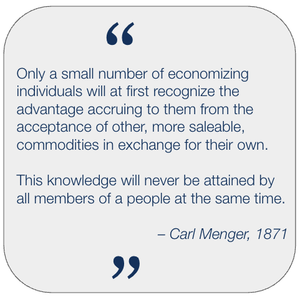
7.4K
トップ
ランキング
お気に入り













